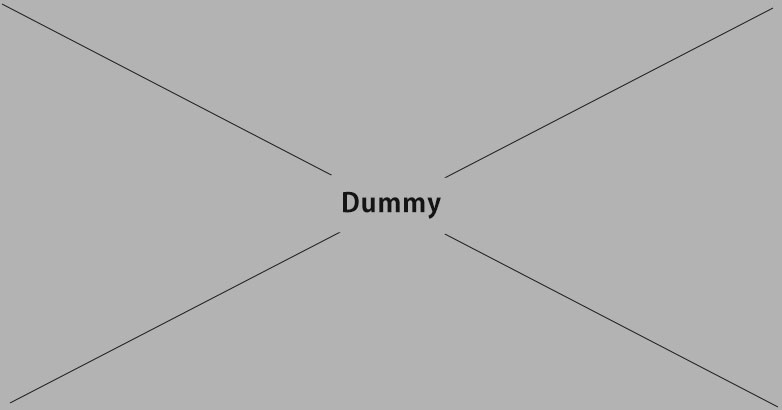カンボジアを訪れる旅行者向けに国内各州の人気観光名所・ホテル・お土産・料理などの(ちょっとニッチな?)観光情報をご紹介。今回は2008年に世界遺産に登録されたプレアヴィヒア寺院がある、プレアヴィヒア州について。
基本情報
プノンペンから国道6、64号線で307km。シェムリアップからはスヴァイルー地区、クレーン地区を経由するのが最適。
面積 14,031km
人口 143,565人
以前この州はトバェンミァンチェイ州といったが、1964年にノロドム・シアヌーク前国王がタイからプレアヴィヒア遺跡の返還を受け、この遺跡や領土をカンボジアのものとして永遠に守るため、プレアヴィヒア州と改名した。プレアヴィヒア州はカンボジア・タイ・ラオスが接する地点で、三角エメラルド地域とも呼ばれる。
中心地(The center of the town)
ワットバッカム(Wat Bak Kam)
1996年に一人の僧侶が「プレアヴィヒア州の人々の安全と健康のために寺を建てるように」というお告げを受けて建立したお寺。人々の祈りの場として親しまれている。
プンオンカムの石(Poeng Angkham Rock)
ワットバッカムへの途中の自然の深い森にある。語源の“プンカーム”は「自然の成り行きに頼る」という意味。フランス植民地時代、重税をかけられていた人々は、税金の催促から身を隠すために、ここへお祈りをしに来た。フランス兵はこの石まで追ってくることはできず、人々は逃げきることができた。以来、この石には効力があるとされ、今なお人々にあつく信じられている。
プレアヴィヒア遺跡(Preah Vihear Temple)
市街から117Kmほどのドンレック山脈の中央よりやや東側に位置する寺院遺跡。タイとの国境に近い標高625mの上に建つ。ヤショーヴァルマン1世(889-900)によって建設が始められ、その後スーリャヴァルマン1世(1002-1050)、ジャヤヴァルマン6世(1080-1107)、スーリャヴァマン2世(1113-1150)によって受け継がれ、偉大なクメール寺院に変貌した。
入り口からは162段の階段を上がり第一遺跡に到着。参道には大きな看板が立てられ、クメール語と英語で「私はカンボジアに生まれたことを誇りに思う」と書かれている。カンボジア人はプレアヴィヒア遺跡観光の際は、かならずこの看板をバックにして撮影する。第4遺跡はとても有名で、信仰のあつい「ディーお爺さん」の祭壇がある。ディーお爺さんは昔、愛国者として有名な兵隊長だった。シャム軍との戦いに負け、地獄の軍隊を徴兵するためにプレアヴィヒアの絶壁から飛び降りたといわれている。彼の愛国心をたたえ、彼の姿を彫刻にしてお祈りをしている。この像に線香をあげて祈ったことは必ず実現すると地元のガイドが教えてくれた。プレアヴィヒア遺跡はクメール・ルージュ時代に支配され、軍隊のキャンプとして利用されたため、当時の大砲が残されているところがある。ユネスコは、来年8月にこの遺跡を世界遺産に登録する予定。カンボジアからの入り口は急な坂道で、ピックアップトラックやバイクで移動する(タイからも入場可能)。遺跡観光の入場料は外国人200バーツ(子供100バーツ)、タイ人50バーツ(子供20バーツ)。カンボジア人無料。
プラム(五つ)遺跡 5 Temples (Neak Buos Temple)
ジャヤヴァルマン4世によって建てられたヒンドゥー寺院。彼は、シェムリアップ州での戦争から逃げて、ここに都を遷した。遺跡はストゥーパのような形の五つの塔があったことから、五つの遺跡(プラサートプラム)と呼ばれるようになった。
道端の遺跡(The remains)
コッケー遺跡(Koh Ker Temple)
ジャヤヴァルマン4世によって建てられたヒンドゥー寺院。トバェンミァンチェイの町から72Km、シェムリアップの町から約110Km離れた森に囲まれている。高さ40mもある石でできたピラミッド型寺院で、7段で構成されている。アンコールワットよりも古い西暦900年代に建立された。
国際障害者協会(Intenational disabled association)
障害者と未亡人の生計を支えるために、1995年にアメリカの支援で創設されたシルクの機織りセンター。プノンペンとシェムリアップのホテルの受注生産をするほか現場でも販売している。
トバェンの滝(Waterfall of Tbaeng)
トバェンミァンチェイの中心街から南へ約17Km、トバェン山の麓にある深い森に囲まれた美しい自然の滝。駐車場から森を眺めながら約500m歩くと滝に出る。
観光局(Tourism Department)

プレアヴィヒア観光情報を得るならこちら。副局長のキット・チャンティーさんは「2007年半年間で国内外から7万人の観光客が訪れ、クメール正月はカンボジア人でにぎわう」という。
(情報:2007年10月)